【許可が必要?】建設業許可が不要な軽微な工事
全ての建設工事において、建設業許可が必要という訳ではありません。許可の必要がない工事として『軽微な工事』がありますが、そのほかにも『建設工事に当たらない』工事も許可は不要です。
こちらのページでは『建設業許可が必要ない工事』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
建設業許可の対象
建設業許可の対象は「建設工事の請負」です。
建設業法上の「建設工事」は土木一式工事や建築一式工事など29の業種に分かれていますが、すべての業種の定義において、建築物や土木工作物を作るまたは解体する、あるいは加工・ 取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだものが工事とされています。
建設業許可が不要な工事とは
建設業許可が不要な工事は、『軽微な工事』または『建設工事に該当しないもの』です。
軽微な工事とは
軽微な工事とは、以下工事のみ請け負う場合をいい、建設業の許可は不要です。
| 土木一式工事等 (建築一式工事以外) | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
| 建築一式工事 | 次の①か②のいずれかに該当する工事 ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み) ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
・『軽微な建設工事』の請負代金の額
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額をいいます。
・注文者が材料を提供する場合
その市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額をいいます。
・工種が異なる工事を請け負った場合
元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。
・単価契約で工事を行った場合
単価×数量の合計額を請負金額とします。
・小口、断続的な契約
それらの合計額を請負金額とします。
・「住宅」とは 「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」(建設業許可事務ガイドライン)をいいます。
・「150㎡未満」の考え方は、建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、「建築物の各階の床面積の合計」を指します。 (建築基準法施行令第2条第1項第4号)。 なお、建築基準法に基づく容積率積算では、共同住宅の共用廊下・階段等を延べ面積に不算入とする例外(建築基準法第52条1項5号、同6項)がありますが、あくまで容積率積算における例外であって、建築基準法上の延べ面積全般に適用される規定ではありません。 したがって、建設業法上の軽微な工事に当たるかどうかの判断においても、この容積率積算上の例外は適用しません。
建設工事に当たらない工事や業務とは
業として建設工事の完成を請け負わない自社制作や、自ら施工し販売する建売住宅、土地の定着物ではない船舶の内部工事などは建設工事に該当しないため、許可が要りません。
なお、経営業務の管理責任者の経営経験や専任技術者の実務の経験として認めることもできませんので注意してください。
| ・炭鉱の坑道掘削や支保工 ・樹木などの冬囲い、剪定 ・街路樹の枝はらい ・道路維持業務における抜開、草刈、除土運搬、路面清掃、側溝清掃 ・建設機器のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸 ・委託契約による設備関係の保守点検のみの業務 ・造林事業 ・苗木の育成販売 ・工作物の設計業務、工事施工の監理業務 ・地質調査、測量調査 ・建売り分譲住宅の販売 ・雪像製作時の足場などの仮説工事 ・家電製品販売にともなう付帯物の取り付け ・水道管凍結時の解凍作業 ・自社社屋などの建設を自ら施工する工事 ・船舶内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事 ・工事現場に人を派遣する(人工出し)業務 ・宅地建物取引業の営業 ・物品の販売 |
建設工事の請負契約とはみなされません。 単に職人を貸すような人工出しは請負ではなく「労働者派遣」に当たります。しかも、建設工事に労働者を派遣することは違法ですので注意してください。 例えば、A 社という建設業者が自社の従業員を発注者 B 社の建設現場に送り込み、B 社の現場監督者の指揮命令のもとに労働力を提供させることは、「労働者派遣」とみなされます。建設工事への労働者派遣は法律で禁止されていて、労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則 (1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されますので注意してください。 なお、1人工につきいくら、といったいわゆる常傭(常用)の契約であっても、建設工事の請負に当たる場合がありますが、具体的には労働局等の監督官庁に御相談ください。
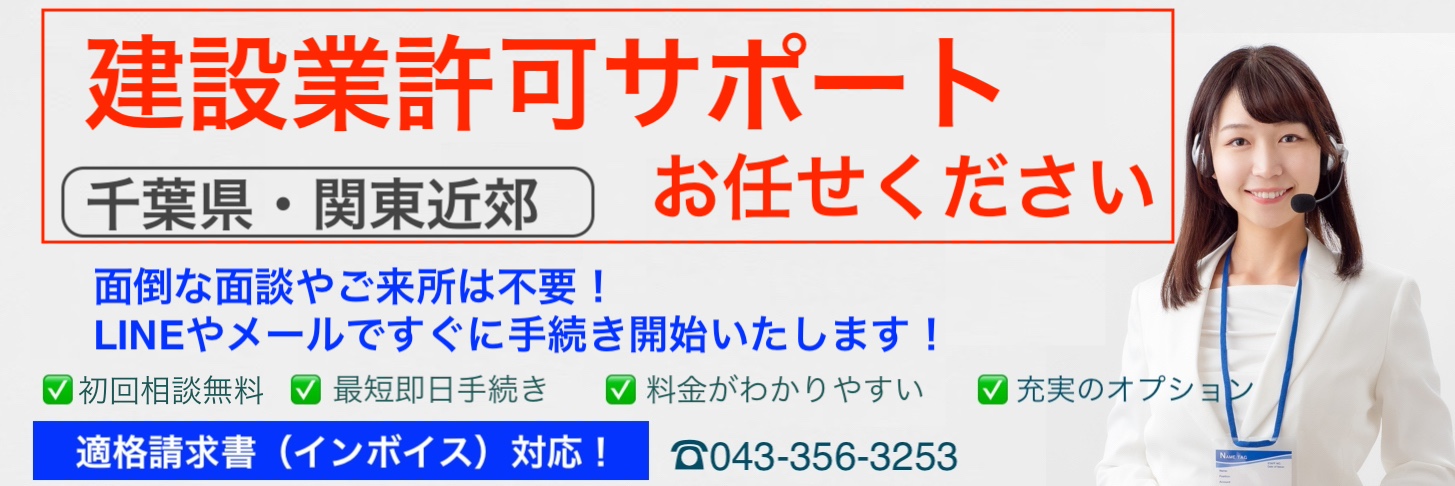


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません